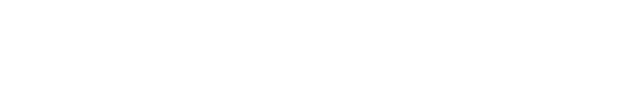SST
SSTとは
SST(エスエスティー)=Social Skills trainingの略称で、社会生活技能訓練とも呼ばれています。
→認知行動療法の一つに位置付けされ、社会(ソーシャル)の中で暮らしていくための技術(スキル)を高めるための訓練の名称のこと。
訓練方法
・社会で暮らすための技術(社会生活技能)を効果的に学習するために構造化された方法。
・ロールプレイ、ディベート、ワークシートなど様々あります。
共有点
・リカバリーの考え方(その人が、その人らしく、納得のいく人生を送れるようになること)を重視。
・社会の中で対人関係を円滑に運ぶための訓練を繰り返し取り組むことで”できること”を増やす。
SSTの広がりと背景
*SSTはもともと、精神に障害を持った人を対象としていた
1940年代の行動療法が原型。
1994年4月精神科を標榜している保険医療機関において入院加療者を対象として「入院生活技能訓練療法」が診療報酬化された。
→対人関係を中心とする社会技能の向上を高める他に服薬自己管理や症状自己管理などの疾病自己管理スキルを高める方法がスキルパッケージとして開発されています。
*現在は精神科領域だけでなく、さまざまな領域で実践されています。
・教育領域
・就労支援関連領域
・矯正教育及び更生保護領域、
・職場のメンタルヘルス(産業領域)
・一般市民など
また、家庭や職場への訪問等、地域生活者の現場で支援も行われています。
社会生活技能の身に着け方
社会生活技能(=社会を営むために必要なスキル=対人スキル)
社会生活技能は家族や周りのひとと関わり、他人の行動の観察と自分の行動から生じる結果との組み合わせによって、学習をして身についていくと言われています。
スキル不足や誤学習などによるエラーが生じた場合、日常でうまく学習ができずつまづく可能性が高くなります。
ひとによって苦手な状況やつまづく場面、スキルアップしたい場面は様々です。
そんな状況や場面を切り取り、SSTという手段を用いて訓練し、対人スキルを高めることがこの時間の目的です。
社会(ソーシャル) 技能の基本スキル
実践を想定して、ロールプレイやグループワークを通して訓練を行うことが多いです。
SSTでは、下記6つの基本スキルが重要だと言われています。

SSTの具体的な内容
①ロールプレイ(役割演技)
日常に起こる課題場面をその場の参加者たちが役割を演じることで課題解決の手がかりを得る方法。
「役割を演じる」という疑似体験を通して、想定された課題場面が実際に起こった時に適切に対応できるようにすることが目的。
<手順の一例>
(1)練習する課題を決める(どのような言動ができるようになりたいか)
(2)練習の場面設定を共有する(いつ、どこで、だれが、どのように行動する場面か)
(3)役割分担を決める(練習場面に登場する相手役など)
(4)ロールプレイ
(5)ロールプレイ後、練習メンバーで「良かったところ」を褒める
※褒めるというフィードバックを通して言語、非言語的コミュニケーション、ものの見方や考え方を強化し、次回以降も同じような良い言動ができるようにする。
(6)更に良くする点(改善点)を考える
※練習メンバーは提案されたものの中から、「取り入れたい」「取り入れられそう」と思う改善点を選択
(7)取り入れる改善点を心に留めながら、再度練習する
(8)よくなった点を褒める
②ディスカッション、ディベート
あるお題に対して、「言葉のキャッチボール」を目的に相手の意見を聞きつつ、自分の意見を述べる練習をしていきます。
※相手を言い負かす”ことが目的ではありません。
③共同行動
療育の現場やデイケアにおいて、工作や調理などの共同作業などの活動を通して他の人の相談、役割分担、助け合いなどの社会的技能を身に着けます。
④ゲーム、レクリエーション
「SSTなのにゲーム?」と不思議に思われる方もいるかもしれません。
ゲームでは「ルールを守る」「勝ち負けを受け止める」「相談・協力」といったスキルが楽しく身に付きます。
⑤ワークシート・絵カード・ソーシャルストーリー
書き込み式のワークシート、図式化された絵カード、ソーシャルストーリーなどをSSTに用いることもあります。
課題になっている言動を文章や図で表現することで、意識化をします。
SSTのメリット
職場の人間関係を円滑にする
きちんと薬を服用することができ、健康な状態を維持する
「嫌だな」と感じる場面できちんと断ることができる……など
基本をおさえれば応用がきくように、様々なケーススタディを通して自分なりの対処法を見つけていける力が身に付きます。
SSTを実践するメリットは、社会生活を営む上での困りごとの解決に役立ち、QOLの向上に繋がることです。
また精神疾患を悪化させないためや二次障害を引き起こさないために活用するのも有効です。
日常で取り入れられるSST
SSTは必ずしも専門知識を持った指導者のもと特別な施設にて行われるだけではありません。
日常でも意識をして取り入れることができます。
例えば…
挨拶をする
挨拶は人とのコミュニケーションの第一歩です。
適切なタイミングで適切な言葉を発することができるようになるため、人によっては練習が必要かもしれません。
意識的に挨拶をしてみましょう。
いきなり「雑談を上手に続けられるように目指す」と高い目標を掲げるよりも、「挨拶をしっかりする」と心がけるだけで周囲からの印象は驚くほどアップします。
相手の気持ちを察する
相手が考えていることを意識的に想像する訓練を、日常的におこなってみるのも大切です。
繰り返し練習を行うことで自然と相手の気持ちを理解できるようになっていきます。
※療育(対:子ども)の場面では人形を用いて「登場キャラクターの気持ちを考える」といったトレーニング方法もあります。
会話をする
感情のコントロールが難しい方は、相手を傷つける言葉を言ってしまったり、相手にとって興味のない話を続けてしまうこともあります。
会話・対話とは相手の話を聞き、意図をとらえ、適切な答えを返す必要があります。
まずはスモールステップで、「一問一答から始めてみる」「台本を用意して会話の練習をしてみる」「フリートークをして、お互いにどう思ったかを振り返る」などから始めてみてはいかがでしょうか?
医療法人社団結糸会 リワークセンターキズナ